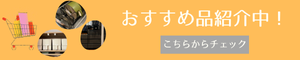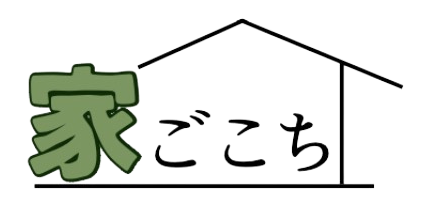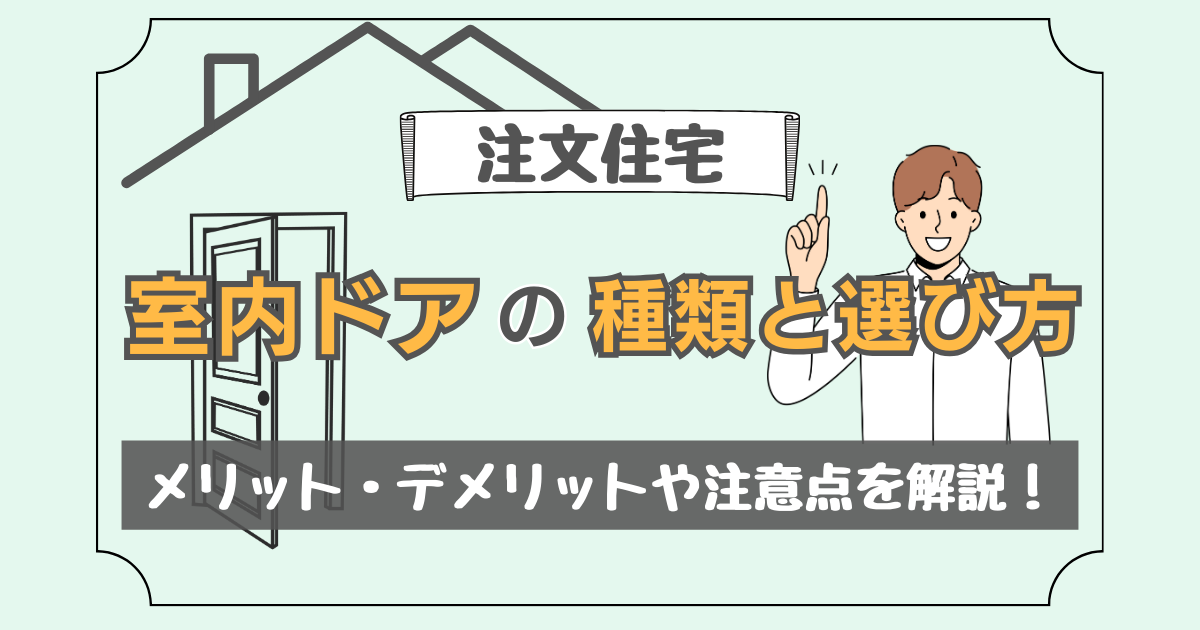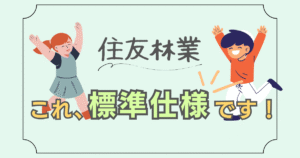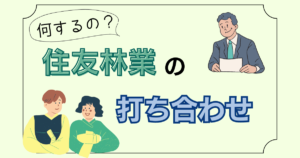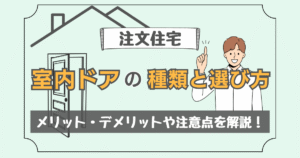こんにちは!住友林業で注文住宅を建てました、あいすです。
今回は、注文住宅の打ち合わせで決めることの一つ、「室内ドアの種類」について解説します。

ドアの種類って、意外とたくさんあるよね。



特徴を理解して、最適な物を選ぼう!
「ドア」は、機能性の面でもデザイン面でも、意外と大事な部分なんです。
とは言え、どうやって選べばいいかわからず、適当に選んでしまいがち⋯
そこで、ドアの種類ごとのメリット・デメリットや、選び方のポイント、注意点などをわかりやすくまとめました!
それぞれのドアの大まかな特徴は、下記の通りです。
| ドアの 種類 | 特徴 |
|---|---|
| 開き戸 | 最も一般的なドアで、前後にスイングして開閉する。 遮音性・気密性に優れている。開閉のためのスペースが必要。 |
| 引き戸 | 左右にスライドさせて開閉するドアで、襖などもこれに該当する。 バリアフリー住宅などにも採用される。 |
| 折れ戸 | 扉を折り畳むようにスライドして開閉するドアで、収納の扉としてよく採用される。 狭いスペースで活躍する。 |
- 室内ドアの種類と特徴
- 種類ごとのメリット・デメリット
- 室内ドアの最適な選び方
それでは、いってみましょう!
注文住宅で使われるドアの種類


注文住宅で使われるドア(室内扉)は、大きく分けて以下の3種類です。
ここでは、それぞれのドアの特徴を紹介します。
スタンダードで比較的安価な「開き戸」


注文住宅において、標準仕様で採用されることが多いのが「開き戸」です。
最もスタンダードな形で、「ドア」といったら「開き戸」をイメージすることが多いのではないでしょうか。
「蝶番」と呼ばれる部品で取り付けられており、ドアを前後に押したり引いたり(スイング)して開閉するのが特徴です。
開き戸の中にも「片開き戸」と「両開き戸」の主に2種類があり、それぞれ以下のような特徴があります。
- 片開き戸
-
扉が1枚のみの、最も一般的なドア。
内開きor外開き、左開きor右開き、といった使い方があり、間取りに応じて選択出来ます。 - 両開き戸
-
観音開きタイプのドア。
狭い廊下などで開き戸を使いたい場合や、パントリーなどの収納用の扉として使われることが多いです。
和室の襖などでも使用される「引き戸」


レールに沿って、ドアをスライドして開閉する「引き戸」。襖や障子などもこの「引き戸」に該当します。
車椅子を使っていても簡単に開閉できるため、「バリアフリー住宅」でもよく採用されています。
注文住宅で使用される引き戸は、主に以下の3種類です。
- 片引き戸
-
1枚の扉を、左右どちらかにスライドして開閉するドアのことで、一般的な家庭でよく見る「引き戸」がこれに該当します。
2〜3枚の扉を連動させて使うタイプもあり、必要に応じて使い分けが可能です。 - 引違い戸
-
2枚以上の扉が設置され、左右交互にどちらにでもスライドできるドア。
左右どちらからでも開閉できる、機能性や柔軟性が魅力です。 - 引き込み戸
-
開けた扉が壁の中に収納される、特殊な形状の引き戸。
開けた状態だと扉が完全に見えなくなるので、スッキリとした空間設計が実現できます。
また、通常の引き戸の場合、引き込みスペースにはコンセントや家具を配置出来ませんが、引き込み戸であればそれも可能になり、空間を有効活用出来ます。
引き戸は、レールの設置方法も以下の2種類に分けられます。
- 上吊りタイプ
-
天井などにレールを取り付けて、戸を上から吊るしてスライドさせるタイプ
- レールタイプ
-
床に敷いたレール上で戸をスライドさせて開閉するタイプ
スペースが狭くても開閉可能な「折れ戸」


扉を折り畳むようにスライドして開閉する「折れ戸」。
クローゼットやパントリーなど、収納の扉としてよく用いられます。
引き込みスペースが必要なく、開閉のためのスペースも最小限で済むため、狭いスペースでも設置できるのが特徴です。
2枚の扉を左右に開く「両開きタイプ」や、複数のパネルを蛇腹状に折りたたむ「アコーディオン式」など、種類も様々です。
ドアの種類ごとのメリット・デメリット


ここからは、ドアの種類ごとにメリットとデメリットを解説していきます。
それでは、具体的に見ていきましょう!
開き戸のメリット・デメリット
開き戸のメリット・デメリットは、下記の通りです。
| メリット | 他のドアより安い場合が多い 気密性・遮音性が高い ペットドアを付けられる |
|---|---|
| デメリット | 開閉のためのスペースが必要 取っ手の出っ張りに注意 ストッパーが必要 |
順番に分かりやすく解説していきます!
メリット
- 他のドアより安い場合が多い
-
具体的な価格はメーカーごとに異なりますが、同じメーカーの同じシリーズであれば、引き戸などよりも開き戸の方が安いのが一般的です。
そのため、注文住宅の標準仕様でも採用されやすくなっています。 - 気密性・遮音性が高い
-
ドア枠に合わせてほとんど隙間なく閉まるような設計になっているため、他のドアに比べて気密性や遮音性が高いです。
実際にご自宅のドアを見てみてください。他のドアよりも、上下の隙間がなく「カチャン」としっかり閉まることがわかるはずです。 - ペットドアを付けられる
-
ペットを飼っているご家庭では、「ペットドアを付けたい」という希望があるかもしれません。
引き戸の場合、ペットと飼い主のタイミングが万が一被ってしまうと、ペットが挟まってしまう恐れがあり危険です。開き戸であればそのようなリスクも軽減できるでしょう。
デメリット
- 開閉のためのスペースが必要
-
開き戸は前後に開く特性上、開閉のためのスペースが必要となります。
そのため、狭い空間での採用や家具の配置には注意が必要です。 - 取っ手の出っ張りに注意
-
大人の腰あたりの位置、お子様の頭の位置に、どうしても取っ手を付ける必要があります。
ドアは動線上にあるものなので、ぶつかって怪我をしないよう、注意が必要です。 - ストッパーが必要
-
勢いよく開いて壁にぶつかったりしないよう、ストッパーがあった方が安全です。
ストッパーの種類も様々で、床やドア枠に金具を取り付けることで、ストッパーの役割を果たします。意匠性や金額面を考慮して選びましょう。
引き戸のメリット・デメリット
引き戸のメリット・デメリットは、下記の通りです。
| メリット | 開け閉めしやすい スペースを有効活用出来る 開けても閉めても使える |
|---|---|
| デメリット | 引き込みスペースが必要 気密性・遮音性が低い 掃除が手間 |
順番に分かりやすく解説していきます!
メリット
- 開け閉めしやすい
-
手前に引いたり奥に押すような動作が必要な、開き戸や折れ戸に比べて、「引き戸」は少ない力かつ最小限の動作で開け閉めが可能です。
お子様や高齢者の方にも開けやすく、また、車椅子の通行も妨げないため、バリアフリー住宅にも多く採用されます。 - スペースを有効活用出来る
-
引き戸は左右にスライドして開閉する設計のため、前後のスペースが必要なく、デッドスペースが少なくて済みます。脱衣所などの狭いスペースに適しているでしょう。
引き込み戸ならさらにスペースを有効に使えます。 - 開けても閉めても使える
-
開けっ放しにしておいても邪魔にならないので、必要なときだけ閉めて、部屋の間仕切りのように使用することも可能です。
また、少しだけ開けておいて、風の通り道を確保するといった活用方法もあります。
デメリット
- 引き込みスペースが必要
-
「引き込みスペース」とは、ドアを開けた時に壁と重なる部分のこと。
扉と同じ面積の引き込みスペースが必要となり、そのスペースに物を置いてしまうと扉が開けられなくなってしまうほか、引き込みスペースの壁面にはコンセントやスイッチも配置できません。
「引き込み戸」であれば、このデメリットはクリア出来ます。 - 気密性・遮音性が低い
-
開き戸と比較すると隙間が多く、気密性・遮音性はあまりよくありません。
隙間風が入ったり音漏れが気になる場合があるので、採用する場所はよく検討しましょう。 - 掃除が手間
-
下にレールが敷かれているタイプの場合、レールの溝にゴミが溜まって掃除しにくいです。
また、引き込み戸の場合、壁内の戸袋にゴミが入り込むと処理が大変なので、こまめな掃除が必要です。
上吊りタイプかつ通常の引き戸であれば、それほど気にならないでしょう。
折れ戸のメリット・デメリット
折れ戸のメリット・デメリットは、下記の通りです。
| メリット | 狭いスペースでも使用可能 開口部を広くとれる |
|---|---|
| デメリット | 指を挟む危険性がある ほこりが溜まりやすい |
順番に分かりやすく解説していきます!
メリット
- 狭いスペースでも使用可能
-
一番のメリットは、ドアの開閉時に必要なスペースが少なくて済むことです。
そのため、廊下などの狭いスペースであっても、折れ戸であれば通行の邪魔にならずに開け閉めすることが出来ます。 - 開口部を広くとれる
-
押し入れのような引違いタイプのドアだと、左右片方ずつしか中を見ることが出来ません。
クローゼットなどに折れ戸を採用すれば、中を一気に見渡すことが出来て使い勝手がいいです。
デメリット
- 指を挟む危険性がある
-
ドアを閉める際に、少し力が必要です。折れ曲がっている部分を手で押すと、勢いよく閉まって指を挟んでしまう可能性があります。
特に小さなお子様のいるご家庭では、注意が必要です。 - ほこりが溜まりやすい
-
扉が折れ曲がっている部分に埃が溜まりやすく、掃除が難しい傾向にあります。
また、下にレールがあるタイプの場合、レールの掃除もする必要がありますが、ドアを全開にすると端に折り重なるようになるため、隅々まで掃除できません。
場所ごとのドアの選び方と注意点


ここまで、ドアの種類やメリット・デメリットについてご紹介しました。
結局のところ一番大切なのは、「どんな場所でどの種類を選べばいいのか」です。
ここからは、ドアの選び方や注意点について、具体的に解説していきます!
寝室・子供部屋は「遮音性」を重視
寝室や子供部屋といった、家族それぞれの「居室」は、いくら家族とは言えプライバシーを確保したいところ。
そのため、ドアは遮音性(防音性)を重視して選ぶのがおすすめです。
遮音性がいいドア:開き戸、遮音性能の高い引き戸など
廊下などの狭い場所では「折れ戸」が活躍
廊下などの狭いスペースには、通り道の邪魔にならないように、「折れ戸」を採用するのがおすすめです。
我が家の廊下の収納は、折れ戸と小さめ開き戸の合わせ技で、ドアを開けた状態でも通路を完全に塞がないような設計になっています。


「引き戸」はインテリアの配置に注意
「引き戸」を採用する場合、インテリアの配置に注意が必要です。
ドアを開けた時に引っかかってしまうので、引き込みスペースに干渉しないようにインテリアを配置しましょう。
「収納のドア」は収納の使い方によって最適なものを
収納のドアは、「何を収納してどれくらいの頻度で使用するか」を考慮し、最適な物を選ぶことが重要です。
たとえば、
- 収納内をまんべんなく高頻度で使うなら、開き戸か折れ戸
- 左右どちらかだけ使うことが多いなら、引き違い戸
- 普段から全開で使用するなら、ドアを付けずに来客時だけカーテンで対応
など、実際の使い方をイメージした上で、間取りと照らし合わせて検討しましょう。
ちなみに折れ戸を採用する場合は、ドアを開けた際に扉が重なる部分があり、その部分の出し入れがしにくくなるので、注意が必要です。
色にもこだわって空間設計を
この記事では、ドアの種類や特徴について詳しく解説しましたが、「おしゃれな空間設計」をするためには「ドアの色」にもこだわりましょう。
とは言え、我が家の場合は、インテリアコーディネーターさんのセンスにほぼお任せしました(笑)
我が家のドアの色は計3色
- リビングは床材に合わせて「オーク」
- 子供部屋は壁紙や収納に合わせて「白系」
- 寝室はグレーの壁紙に合わせて「グレージュ」
住友林業は「ハイドア」+「ソフトクローズ」が標準


住友林業の場合、標準仕様で採用できる室内ドアはすべて「ハイドア」と「ソフトクローズ」の仕様になっています。
- ハイドア
-
垂れ壁がなく、天井までの大きなサイズのドアです。垂れ壁がないことでスッキリとした空間になります。
- ソフトクローズ
-
ドアがゆっくり閉まる仕様です。急に「バタン」と閉まることがないため、指を挟んでしまう危険がなく、安全性に優れています。
住友林業では追加料金無しでこの機能が付いていましたが、気になる方は担当の営業さんに聞いてみてくださいね。
オプション仕様の場合増額になることがほとんどだと思いますが、意匠性・機能性の両面でおすすめです!
住友林業の標準仕様については、こちらをチェック!
まとめ【最適なドアを選んで住み心地のいい家へ】
今回は、注文住宅で使われるドアの種類と特徴、選び方や注意点についてご紹介しました。
まとめると、以下の通りです。
| メリット | デメリット | おすすめポイント 注意点 | |
|---|---|---|---|
| 開き戸 | 他のドアより安い場合が多い 気密性・遮音性が高い ペットドアを付けられる | 開閉のためのスペースが必要 取っ手の出っ張りに注意 ストッパーが必要 | 気密性・遮音性に優れているので、居室やトイレのドアに最適 狭い場所への設置には注意が必要 |
| 引き戸 | 開け閉めしやすい スペースを有効活用出来る 開けても閉めても使える | 引き込みスペースが必要 気密性・遮音性が低い 掃除が手間 | 開けっ放しにしても邪魔にならないので、柔軟な使い分けが可能 インテリアの配置には注意が必要 |
| 折れ戸 | 狭いスペースでも使用可能 開口部を広くとれる | 指を挟む危険性がある ほこりが溜まりやすい | 開閉時にスペースをとらないので、狭い場所への設置に最適 収納のドアで採用する場合、デッドスペースに注意 |
今回ご紹介した「室内ドア」以外にも、様々な種類やデザインのドアが存在します。
あなたの生活スタイルや用途に合ったドアを選びましょう。
当サイトでは、住み心地の良い家をつくるために役立つ情報を発信しています!
- 注文住宅の打ち合わせについて
- 住宅ローンについて
- 引っ越しまでのスケジュールについて
など、様々な記事を投稿していますので、家づくりの参考にしていただけると嬉しいです。



あなたの家づくりを応援しています!
最後までお読みいただき、ありがとうございました。